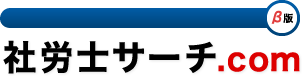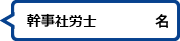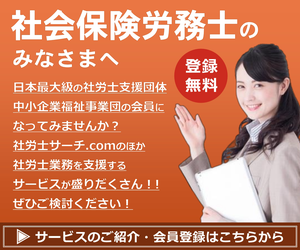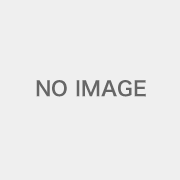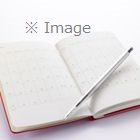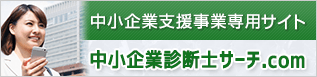- 東京都
レジリエンス社会保険労務士法人
清水 光彦

就業規則雇用管理女性・高齢者・非正規労働者等人事・賃金制度労務問題安全衛生助成金社会保険・福利厚生
「人財」が企業を成長させていきます。
成長する企業には、成長に合わせた人事労務を。
当社では、労働・社会保険諸法令に則った手続き業務のみならず、幅広い業種に対応した人事労務コンサルティングを提供しています。
保有資格
CFP
経歴・実績
東京都社会保険労務士会 常務理事
東京都社会保険労務士会 山手統括支部長
| 所在地 | 〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-25-20 下北沢駅前共同ビル4階 |
|---|---|
| 対応可能地域 | 東京都 |
| 得意業種 | 小売業, 卸売業, 飲食業, 情報、通信業, 医療、介護福祉業, 教育業, 金融、保険業, 製造業, 建設業, および 運輸業 |
| 得意業務 | 就業規則, 社内規定, 労使協定, 雇用管理, 女性・高齢者・非正規労働者等, 人事・賃金制度, 賃金制度, 給与・賞与, 退職金制度, 労務問題, ハラスメント, 安全衛生, 労働災害, 助成金, 社会保険・福利厚生, 健康保険, 厚生年金, 労災保険, および 雇用保険 |
| 得意事業規模 | 1~10人, 11~30人, 31人~50人, 51人~100人, 101人~300人, 301人~500人, 501人~1,000人, および 1,000人以上 |
| WEBサイト | https://www.resilience-sr.jp |
ちょっとした疑問もすぐに解決できます。
お気軽にご連絡ください。