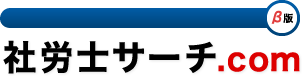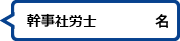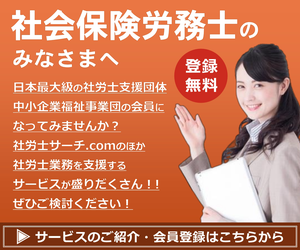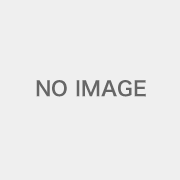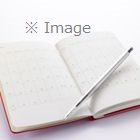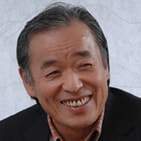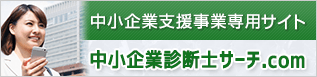- 広島県
山本社会保険労務士事務所
山本 信春

人事・賃金制度
「企業は人なり」は今後さらに重要なキーワードとなります。企業戦略が優れていても、そこに働く従業員が能力不足、やる気不足では片肺運転となり、熾列な企業競争に負けてしまいます。人事制度は、単に給与額を決定するのみではなく、従業員のやる気を出させ、能力を向上させ、そして成果を上げさせるしくみでなければなりません。
機能的な人事制度を構築・運用するためのサポートを重要な仕事として位置づけ、当事務所は企業の人事管理に関わって行きたいと考えております。
保有資格
税理士 行政書士
経歴・実績
国税専門官として税務署に勤務した後、平成5年に、社会保険労務士として開業、平成14年に税理士、平成18年に行政書士も登録開業しました。現在、企業の税務、社会・労働保険に関して申告・手続を中心に行っており、人事制度の構築・運用の指導等も実施しております。
| 所在地 | 〒720-2126 広島県福山市神辺町字徳田1167-9 山本社会保険労務士事務所 |
|---|---|
| 対応可能地域 | 広島県全域 山口県全域 岡山県全域 島根県全域 鳥取市全域 |
| 得意業種 | 小売業, 卸売業, 飲食業, 情報、通信業, 医療、介護福祉業, 教育業, 金融、保険業, 製造業, 建設業, および 運輸業 |
| 得意業務 | 人事・賃金制度, 人事考課, および 賃金制度 |
| 得意事業規模 | 1~10人, 11~30人, 31人~50人, および 51人~100人 |
| WEBサイト | http://www.n-yama-lssa.com/ |
ちょっとした疑問もすぐに解決できます。
お気軽にご連絡ください。