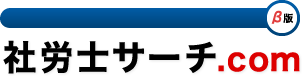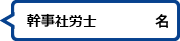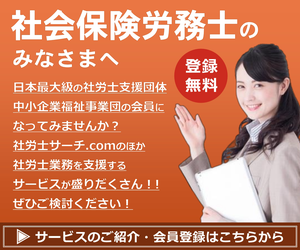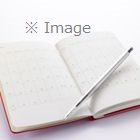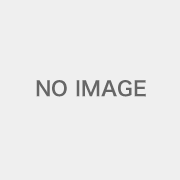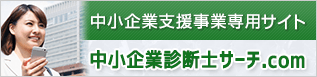- 東京都
社会保険労務士法人ジオフィス
志賀 直樹

就業規則労務問題助成金
日々、孤独な意思決定を繰り返している社長さんにとって、本当に信頼できる外部の相談相手は、いるようでなかなかいないのが現実のようです。
ジオフィスはいつでも傍らに寄り添って「人」の問題の悩みを共有し、社長の最良の相談相手となります。まずは社長の思いを膝を交えじっくりとお聴かせください。
また、顧問社労士としての継続的な関わりを通して、社長や従業員さんのことを理解し、両者の橋渡し役になることを心掛けています。
互いに気持ちが通じ合った、働きがいのある職場づくりを目指します。
保有資格
特定社会保険労務士 キャリアコンサルタント 産業カウンセラー 生産性賃金管理士 日商簿記1級
経歴・実績
昭和42年生まれ。明治大学商学部卒。血液型B型。民間企業役員を経て現職。自分自身、「人づかい」には長年苦労してきたため、「仕事とは何か?」「人間とは何か?」を探求。その結果たどり着いた独自の理論を駆使し、中小企業の発展を助け、日本の未来をもっと明るくするために「志賀社会保険労務士事務所」を開設した。現在は「社会保険労務士法人ジオフィス」に組織変更し、鋭意活動中。
| 所在地 | 〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-18-5 エーム立川204 |
|---|---|
| 対応可能地域 | 東京都・埼玉県・神奈川県 |
| 得意業種 | 卸売業, 情報、通信業, 医療、介護福祉業, 人材派遣業, 金融、保険業, 建設業, および 運輸業 |
| 得意業務 | 就業規則, 労使協定, 懲戒, 採用, 教育訓練・能力開発, 労働時間・休日休暇, 人事異動, 休職, 労務問題, ハラスメント, あっせん調停, 助成金, 健康保険, 厚生年金, および 労災保険 |
| 得意事業規模 | 1~10人, 11~30人, 31人~50人, および 51人~100人 |
| WEBサイト | http://shiga-office.com |
ちょっとした疑問もすぐに解決できます。
お気軽にご連絡ください。