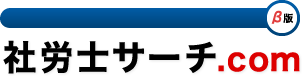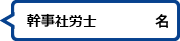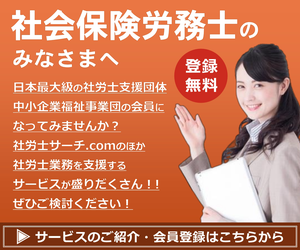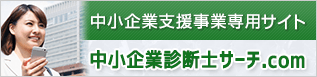- 長崎県
楠本人事労務研究所
楠本 一紀

就業規則雇用管理人事・賃金制度労務問題社会保険・福利厚生労務相談就業管理
楠本人事労務研究所は、会社の【人】に関するあらゆるお悩みについて事業主のパートナーとして問題解決に努めます。
昭和・平成に渡って、【人】の問題の多くは軽視されてきました。
それは、日本人の美徳とも言われる我慢の上に成り立ってきたものです。
しかし令和の時代ではインターネットの発達や働き方改革等の制度改正と共に、労働者が声をあげやすい世の中に変わりつつあります。
これまでの意識で【人】の問題を軽視したまま会社の経営を続けていては事業拡大や新規事業を行おうとした際に、多額の未払い賃金請求や、解雇された従業員の地位確認請求の訴えによって足踏みしてしまうことに繋がります。
今後も楠本人事労務研究所では、【人】に関する専門家として時代に合った最新の技術や知識を取り入れ続け、お客様に還元していきます。
そして、お客様が健全な形で事業の成長を促進できるよう、お客様の目線に立ったご提案を大切に、事業を推進して参ります。
経歴・実績
大学卒業後、日本有数のエア圧縮機メーカーで設計開発業務に従事、工場でも組立指導を行った他、社会保険労務士法人、社会保険労務士事務所で人事労務の経験を経て、2023年に社会保険労務士事務所を長崎県佐世保市で開業いたしました。



| 所在地 | 〒857-0037 長崎県佐世保市石坂町180-29 |
|---|---|
| 対応可能地域 | 長崎県(対面可) 全国(基本オンライン対応) |
| 得意業種 | 小売業, 卸売業, 飲食業, 情報、通信業, 医療、介護福祉業, 教育業, および 製造業 |
| 得意業務 | 就業規則, 社内規定, 労使協定, 服務規律, 懲戒, 雇用管理, 人事・賃金制度, 人事考課, 賃金制度, 給与・賞与, 退職金制度, 労務問題, ハラスメント, 解雇, 未払い残業, 社会保険・福利厚生, 健康保険, 雇用保険, 福利厚生, 労務相談, および 就業管理 |
| 得意事業規模 | 1~10人, 11~30人, 31人~50人, 51人~100人, および 101人~300人 |
| WEBサイト | https://kusumotosrlab.jp/ |
インタビュー
中心とされている業務についてお伺いします。
労働保険・社会保険の各種手続き代行や、給与計算、就業規則の作成・改定などのアウトソーシングを中心業務として取り扱っています。それに加え、社員の定着や活躍を支援する専門家として、採用・定着支援にも力を入れているのが当事務所の特徴です。
社会保険労務士といえば、法律に則った人事労務の専門家というイメージが強いかもしれませんが、当事務所ではその枠を超え、企業の成長を見据えた支援を行っております。特に「良い人材を採用し、定着させ、戦力として活躍してもらう」ための仕組みづくりをサポートすることで、企業の成長に貢献したいという想いで業務にあたっています。
採用・定着支援への注力にあたって、どんな点を意識されていますか。
「そもそもどういった人材を採用したいのか?」という点を、一からお客さまとお話しして洗い出す、という点です。
お客さまご自身が採用のノウハウをどこまでお持ちなのか、という点も勘案しながら、必要とされる職種や雇用形態に合った人材像を形作っていきます。形作った人物像を基に、例えば「求人票にはこういった内容を書いて、こういった訴求の仕方をすると効果的ですよ」というコンサルティングも実施しています。
また、面接指導なども積極的に行っています。昭和・平成の時代ではいわゆる「圧迫面接」が行われることもありましたが、率直に申し上げて、令和の時代ではそれでは良い人材は雇用できません。当事務所では、応募者に自社のファンとなってもらうことで、採用後のミスマッチを防ぐ支援も実施しています。
顧問先には、どのような業種のお客さまがいらっしゃいますか。
業種で見れば「千差万別」という言葉がぴったりで、例えば卸売業や建設業、小売業、飲食業など、幅広い業種のお客さまに対して支援をしています。
また、医療業界が抱える様々な問題解決をサポートする医療労務コンサルタントとしても認定を受けていますので、今後は医療業のお客さまに対しても、支援を拡大していきたいと考えています。
社労士を目指したきっかけをお聞かせください。
実は当時はメーカーで開発職として勤務していて、社労士の業務分野とは無縁でした。ある日、職場の休憩制度に関する雑談の中で、休憩に関する自社の制度が「法律に基づいて決められている」という話を耳にしたんですね。ただ、その制度が残業をするときだけに適用されるピンポイントな内容だったので、本当にそのような法律があるのか調べたところ、そうした内容は法律には明記されていないことを知りました。
この経験をきっかけに、「働いている人たちが自分たちの労働法の内容をあまり知らない」という現実に直面し、それなら自分は「知っている側に立ち、そして正しい情報を届けられる存在になりたい」という想いが芽生え、社労士を目指すようになりました。
開業後、どのようなことに苦労されたでしょうか。
開業にあたって、完全なゼロベースの状態で私のことを知ってもらうというのが本当に大変でしたね。佐世保は地元ではあるのですが、お話ししたメーカー含む私のキャリアすべてが関東でしたので、知人も仕事のつながりも全くない状態でのスタートだったんです。
その中でもホームページを開設するなどして積極的な情報発信に努め、情報をご覧になったお客さまからお問い合わせをいただき、就業規則の改定業務を依頼いただけました。そのようにお預かりした業務でしたので、大切に対応させていただいた結果、社労士として最初の顧問契約を結んでいただくに至った時は、とても嬉しかったですね。
今では情報発信に、各種SNSも活用されているのですね。
はい。Instagramの投稿やホームページ内のコラムなど、すべて私自身が企画・執筆しています。発信内容は、私の関東での社会人経験や、佐世保で開業して感じた地域性の違いなど、自分の体験に基づいたものです。特に、先述した「圧迫面接」がまだあるように、都会と地方では経営者の「人」に対する考え方に大きな違いがあるのを感じていて、それを伝えることが地方企業の役に立つと考えられた際には、強い言葉で改善の必要性を訴えることもあります。
実際に、発信をご覧になって共感してくださる方もいて、「時代が変わっていることに気づいた」と言っていただけることもありますが、本当に情報を届けたい層にはまだ届きづらいのが現状です。今後の課題としては、より多くの方に届くよう、発信力そのものを高めていく必要があると感じています。
地元での開業と伺いましたが、やはり佐世保地域のお客さまが多いでしょうか。
はい。基本的には佐世保を中心とした、長崎県内のお客さまが多いです。対面で相談できる距離感や、地域の空気感・雰囲気を理解していることが信頼関係の構築につながることが多く、「地域密着」は社労士という仕事の特性上切っても切り離せない要素だと考えています。
もちろん、長崎県外のお客さまも一定数いらっしゃり、島根県や新潟県など遠方のお客さまからのご依頼もいただいております。「遠くの社労士より、会える近くの社労士」をベースにしつつ、安心してご依頼いただけるよう努めてまいります。
お客さまへの対応にあたって、心がけていることはありますか。
社労士として提供できるのが無形物、つまり「目に見えにくいサービス」だからこそ、価値を感じていただけるような、プラスアルファの対応を大切にしています。
たとえば就業規則は、単にコピー用紙に印刷して送るのではなく、しっかりとしたファイルにまとめ、手に取って読みたくなるような形でお届けするよう工夫しています。実際に「こんなにしっかりしたものだとは思わなかった」と喜んでいただけることも多くあります。
サービスも決して安価ではないですが、大切なお客さまの業務をお預かりしているので、そうした心がけは今後も継続したいと考えています。
今後の業務の展望も気になるところです。
まず1つは「事業承継」の分野に力を入れていきたいと考えています。
特に地方では、高齢の経営者が事業を誰にも継げないまま会社を閉じてしまうケースが少なくありません。しかし、自分が築き上げた会社を何らかの形で残したいという想いは、多くの経営者に共通していると感じます。その想いを叶えるべく、会社を次の世代につなぐお手伝いができたらと思っています。
加えてもう1つ取り組みたいのが、「労務監査」の分野です。
先ほど述べたスムーズな承継のためには、会社の内部体制が整っていることが不可欠であると考えるからです。法令順守の状況を「見える化」し、承継にあたって外部に対しても安心感を与えられるような体制づくりを後押しできるよう、取り組んでまいります。
ここで、先生の趣味についても伺います。
最近は気分転換を兼ねて、筋トレやドライブを楽しんでいます。筋トレは以前関東にいたころに始めたもので、少しの休止期間を経て、現在はウエイトトレーニングを少しずつ再開しています。ドライブでは、福岡や佐賀の呼子などへ出かけ、美味しいものを味わうことも楽しみのひとつです。
また、今後の計画として、経営者仲間が所有する田んぼで農業体験をすることも考えており、自然の中で身体を動かす時間も持ちたいなと思っています。
最後に、お客さまへのメッセージをお願いします。
情報社会が進化し、経営者も従業員も簡単に知識を得られる時代になりました。便利になった一方で、昔ながらの感覚で経営をしていると、思わぬトラブルに巻き込まれることも増えてきています。実際に、従業員の方が法律に詳しく、知らないうちに経営者がリスクを背負っていたというケースも最近では珍しくありません。
企業を構成する要素として、人・物・金・情報が挙げられますが、最も扱いが難しく、だからこそ重要なのが『人』だと考えています。当事務所は、そんな『人』に関わる課題を一緒に考え、お客さまを支える存在でありたいと考えています。いまお困りのことがある場合でも、今すぐお困りでなくこれからに備えてという場合でも構いません。お気軽に当事務所へご相談ください。
ちょっとした疑問もすぐに解決できます。
お気軽にご連絡ください。